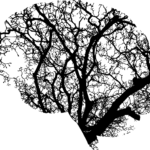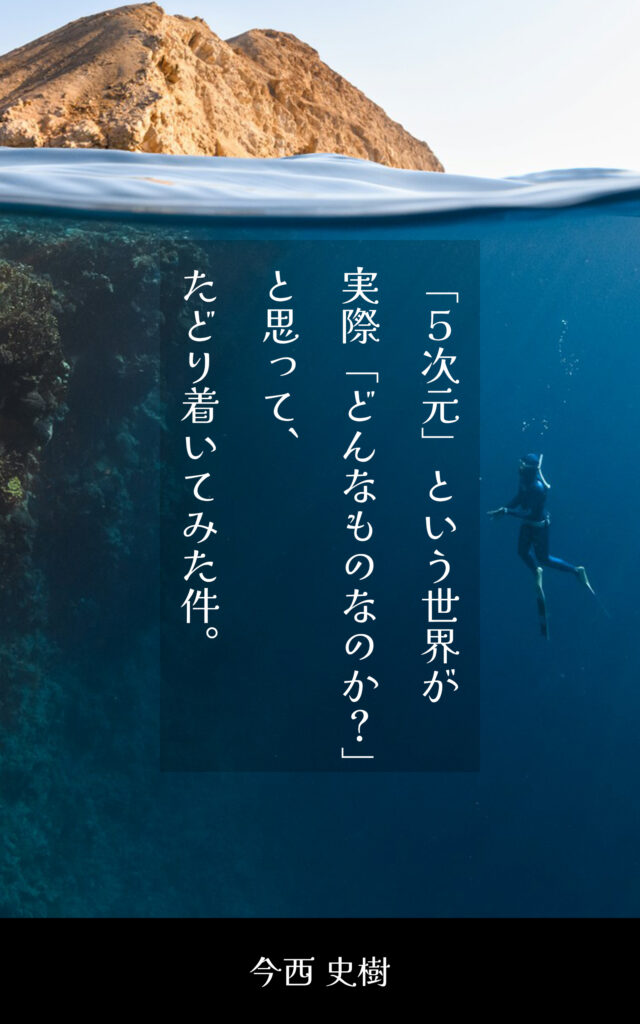2019年12月3日に厚生労働省が体罰についてまとめた方針案を作ったみたいです。
そこには、「これが体罰ですよ」という明確な基準を作ったらしいのですが、明確な基準を作ったから体罰がなくなるのか?というとそんなことはないはずで、そもそもその基準や方針案自体の存在によって、苦しむ人は逆に増えるんじゃないかと思います。
それは、「比べる」基準ができてしまって、それによって自分の「できること」「できないこと」の判断をすることになり、できていれば安心、できていなかったらダメという、ものすごく短期的でどちらに転んでも「不安」が消えることはない状況になってしまいます。
では、なぜ「体罰」というものがあるのか。
なぜ、そもそも体罰が必要か必要ではないかを論じる必要があるのか。
根本的な問題はどこにあるのか。
それらについて書いていこうと思います。
体罰が起こる原因は、「子どもは何も知らない」という価値観を持っているから。

子育てについてはたくさんの方法がありますし、どれが正解というものがないので、自分に合った方法を見つけるしかありません。
ただ、どんな方法をしたのか?ということは、案外大事ではなかったりします。
それは、「子どもは知らないから教えないといけない」「立派に育てないといけない」という価値観から来ていることを知る必要があるのです。
つまり、方法論をいくら変えても、根底にある考え方や価値観が変わらなかったら、起こる結果としては何も変わりません。
例えば、「勉強しない」という子どもを見て、どうすれば勉強するようになるのか?
ということを一生懸命考えて、「言い方」を変えてみたり、「ご褒美」で釣ってみたり、「体罰」で無理やり動かしてみたりしても、勉強しない行動はきっと変わりません。
変わらないから、「どうすれば言うことを聞いてくれるのか」という視点になってしまうので、目的が子どもに自分の言うことを聞かせるということにすり替わってしまいます。
これでは、体罰がエスカレートするのは目に見えていますよね。
ちょっとの力では動かないことがわかったら、それ以上の力を使うことになります。
だから、体罰が大きくなっていくのです。
では、そうなる前に子どもが言うことを聞けばいいと思いますか?
ここで考えてみてほしいのは、アナタが子どもであったとして、言うことを聞かないからという理由で殴られたら、どんな気分になりますか?ということです。
それと同じことを子どもも感じています。
そう感じた子どもが、アナタの言うことを進んで聞くなんてことはあり得ると思いますか?
たぶんないと思います。
でもそれをしているんです。
子どもだからいいとか、それが子どものためだとか、そういうことを言っても、体罰をしている動機自体が、「自分の言うことを聞かせるため」だとすれば、それは、まったく子どものためではないですよね。
勉強をしないと将来困るから。
勉強しないと先生に怒られるから。
こういった動機があると思うかもしれませんが、これも子どもためではありません。
勉強することが素晴らしいという価値観を持っている親が、それを達成できないことに対しての不満から来ています。
ということは、子どものためではありません。
自分が自分の理想とする姿、状態を作れていないから、それを子どもに無理やりやらせようとしているのです。
だから苦しくなります。
無理やりというのは、力ずくになるので、そのために体罰という方法をとらざる負えないということにもつながっていくのです。
これでは、親子それぞれがまったく楽しくない、苦しい毎日になるだけです。
勉強に必要性を感じていないけど、社会の風潮的にそれがいいとされているからやらせようとする親御さんも、それをもとに、けんかになったり、言い争うになったり、関係が悪くなるお子さんも、どちらにとっても全くメリットがない状態が生まれてしまいます。
ではどうすればそれを解決することができるのか。
それらについて書いていこうと思います。
子どもとどう接すればいいのか?

まず、大事なのは、親だからとか、子どもだからとか、そういう価値観を脇に置いて下さい。
「親だからこうしないといけない。」
「親としてこうあるべきだ。」
この価値観は、アナタを苦しむ方向に持っていくことになります。
「子どもだからこうしなさい。」
「子どもだったらこうあるべきだ。」
これもまた、アナタを苦しい方向に持っていくことになるのです。
それは、こうしなさい、こうあるべきだという1つの決まった価値観は、それ以外を良しとしないので、何が何でも決まった枠に押し込もうとしてしまいます。
なにより、押し込んでいる先の答えに対して、自分が心から「いい!」と思えるものであれば、不満も苦しさも出てきませんが、そうではない今回のように厚生労働省が決めたことだから、誰かが決めたことだから、権威のある人が言っていることだからと、無条件に受け入れて、それを疑いもせずに「それが素晴らしいことだ」と受け入れるから苦しさを感じることになるんです。
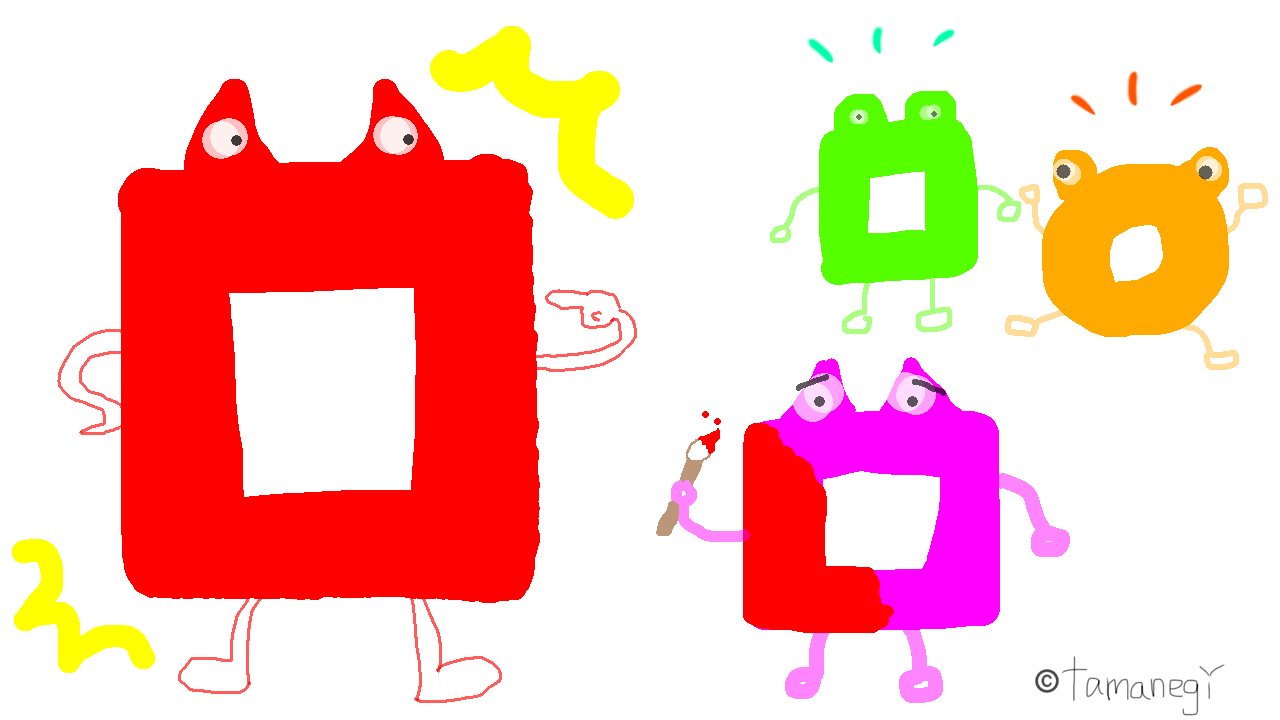
ここでちょっと考えてほしいのですが、アナタが子どもの時に「楽しかった時間」はどんな時間ですか?
「苦しかった時間」はどんな時ですか?
そして、今のアナタが「楽しい時間はどんな時ですか?」「苦しい時間はどんな時ですか?」
ここに間違いなく共通点があると思います。
子どもの時は、きっと家族みんなで楽しく過ごしているときは、楽しい時間になったと思いますし、けんかしていたり、言い争っている時間は苦しかったのではないかと思います。
そして、どちらを生きていきたいのか?ということを考えてもらえば、どちらがいいかわかるはずです。
ここで大事なのは、例えば、子どもが勉強している姿を見て、アナタも子どもも楽しいかどうかということです。
アナタは楽しいですか?
子どもも楽しそうですか?
アナタが自分が子どものときに楽しかった時間は、アナタが勉強している姿を親に見せているときでしたか?
それを考えてみてください。
きっと、「なんで、そんな体罰までして勉強をさせようとしていたんだろう」と思えると思います。
ここまで考えられると、「そもそもなぜ、勉強をさせないといけないのか?」ということを考えられます。
すると、本当にアナタが思い描いている家族の姿を思い出せると思うのです。
そこに体罰ってありますか?
ないと思います。
ガイドラインに明確化されなくても、アナタが思い描いている家族が笑顔で過ごしている時間を、今の現実に作ることができれば、体罰なんて気に留めないくらいのものになるはずです。
肩ひじ張って、「子どもにしつけをしないと」とか、「教えてあげないと」とか、そういうことを思っているから、「言うことを聞かせる」というミッションが出来上がるだけで、本来それは、家族が笑顔になるために必要なことか?ということを考えていれば、必要ないと思えるのではないかと思います。
すると、自然と体罰をするような出来事は起こらないので、必要なくなります。
何回も注意しても聞かないときはどうする?

何回も注意して聞かないというのは、あくまで親の目線でしかありません。
ここで抜け落ちているのは、子どもの目線です。
子ども目線になるためには、自分が逆の立場になって考えてみるのが1番わかりやすいと思います。
これはアナタも同じだと思いますが、何回も注意されるときってどんな時ですか?
たぶん興味がないことを言われた時だと思います。
これは仕事でもそうで、楽しい仕事だったら何度も言われなくても覚えられます。
でも、楽しくない、興味がない仕事のときは、覚えられないんです。
趣味もそうですよね。
電車が好きな人は駅名を覚えていますが、興味がなかったら何度通っても覚えることはありません。
これが注意することも同じだということです。
つまり、アナタの注意を子どもが聞かないのは、それに興味がない、もしくは必要だと思っていないからなのです。
ここで大事なのは、必要であれば子どもは必ず聞いてくるということです。
先々に必要になることがわかっていて、それを先回りして教えてあげるというのは、教えるということではありません。
それは、RPGゲームをしていて、横から急に答えを言われてシラケるのと同じだということです。
つまり、そのときに子どもにとっては必要ないことだから、何度注意しても聞かないんです。
そこで必要なのは、「たたく」などの行動ではなく、「なぜ必要なのか?」ということをしっかり説明することになります。
そもそも、「なぜ必要なのか?」ということを説明できないことを子どもに注意すること自体おかしいということに気が付いたほうがいいと思います。
大人ですら、「なぜ必要なのか?」がわかっていないことを、子ども押し付けるということは、ナンセンスです。
これも逆の立場になってもらったらわかると思います。
「なぜ必要なのか?」というところがないから、何度注意しても聞かないんです。
逆に言えばそれだけのことです。
しっかりとした理由があって、なぜ必要なのかを明確にしていれば、それは子どもだけに関わらず、話は聞いてくれるのです。
例えば、この辺りは部下や社員が言うことを聞かないとも同じ理由ですね。
聞いてくれない原因を相手に求めることはできません。
だから、自分の中を整理して明確にしない限り、体罰をしたところで何の解決にもならないことに気が付いてみてください。
まとめ
体罰は、楽しく生きるために必要なことではありませんし、楽しく生きていれば体罰自体の議論もなくなります。
必要かどうかを考えている時点で、楽しく生きることを放棄していることに気が付いてください。
そして、自分の何気なく考えていることや常識に対して、楽しくなく苦しいと思うのであれば、「なぜ?」という疑問を持ってみてください。
きっと、矛盾点や不思議なことが見えてくると思います。
楽しく生きるためにやっていることが、気が付いたら目的が変わっていた・・・
ということがわかれば、もう一度目的を考え直すことにもなります。
少なくとも、みんな「楽しく生きたい」と思っているはずなので、そのうえで必要なことは何か?
どういう状態なのか?を考えていけば、自然と何が必要なのか?ということはわかっていくと思います。